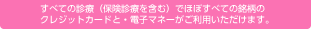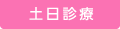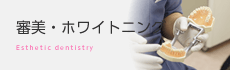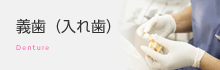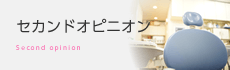2月, 2019年
舌が白いのと口臭は関係がある? [2019年02月14日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「口臭の原因について」です。口臭がするからには必ず原因があり、最も分かりやすいのは食材によって起こる口臭ですね。 例えば、ニンニクを使用した料理を食べれば、いくら歯 […]
歯が痛い時は虫歯か歯周病かどちらでしょうか?それぞれの違いは何ですか? [2019年02月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「歯の痛みの原因と虫歯と歯周病の違い」です。歯が痛い時、その原因として考えられるのは虫歯か歯周病です。 ただしこれは可能性の話であり、実際には他の原因で痛んでいるの […]