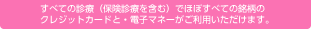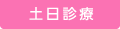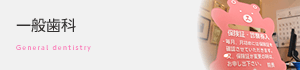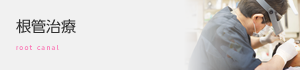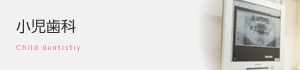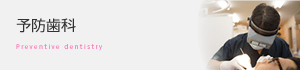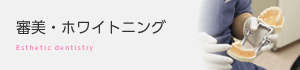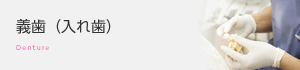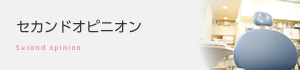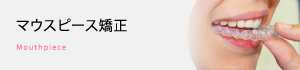BLOG
歯並びが悪いと頭痛になりますか? [2019年04月15日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「歯並びと身体の健康について」です。 歯並びが悪いと口元の見た目が悪くなる…それは誰もが想像できるでしょう。 実際、口元の見た目を美しくするために矯正治療を希望す […]
歯周病と口が臭いのは関係ありますか? [2019年04月01日]
江東区門前仲町の歯医者、良修会 原澤歯科です。今回のテーマは「歯周病と口臭の関係」です。 身体に何らかの症状が起こった時、それは身体が異常を伝えるためのSOSのサインです。 例えばお腹を壊した時、それは腹痛という症状でS […]
歯周病は細菌によるものなのですか? [2019年03月15日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「歯周病の説明」です。まずタイトルの質問に回答すると、歯周病はその原因菌による感染で起こります。 ですから、歯周病は細菌によって起こるものであることに違いありません […]
出っ歯だと噛み合わせも悪いですか? [2019年03月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「出っ歯の原因と問題点と治療方法」です。噛み合わせが悪いと言ってもその状態は様々で、見た目では判断できないこともあります。 一方、見た目で判断できるのは歯並びが悪い […]
舌が白いのと口臭は関係がある? [2019年02月14日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「口臭の原因について」です。口臭がするからには必ず原因があり、最も分かりやすいのは食材によって起こる口臭ですね。 例えば、ニンニクを使用した料理を食べれば、いくら歯 […]
歯が痛い時は虫歯か歯周病かどちらでしょうか?それぞれの違いは何ですか? [2019年02月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。今回のテーマは「歯の痛みの原因と虫歯と歯周病の違い」です。歯が痛い時、その原因として考えられるのは虫歯か歯周病です。 ただしこれは可能性の話であり、実際には他の原因で痛んでいるの […]
頭痛と噛み合わせはどう関係しているのですか? [2019年01月15日]
いつもお世話になっております。門前仲町の歯医者、良修会 原澤歯科です。 今回のテーマは「噛み合わせの悪さの問題」です。 社会人の方にとって、頭痛はたびたび起こる体調不良の一つではないでしょうか? 頭痛薬では頭痛の原因の解 […]
原因が分からず、歯がグラグラしていて抜けそうなのですが歯周病ですか? [2019年01月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「歯周病について」です。歯がグラグラと不安定になっている場合、その原因としていくつか考えられることがあります。 例えば、歯をぶつけた場合に衝撃の強さによっては歯が […]
口を開けるたびに顎の関節がなるのが気になります。何が原因なのでしょうか? [2018年12月15日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「顎の関節の病気」です。顔の箇所ごとで病気を考えた時、最も深刻に考えないのは顎ではないでしょうか。 頭の病気は言うまでもなく深刻ですし、目の病気においても同様のこ […]
口臭が出やすい人の特徴を教えてください [2018年12月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「口臭がしやすい人の特徴」です。みなさん、これまで一度は人の口臭が気になった経験があると思います。 そんな口臭が気になった時のことを振り返ってみると、口臭がするの […]