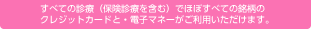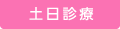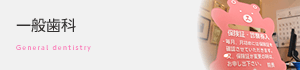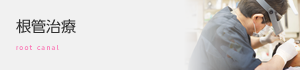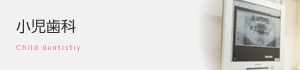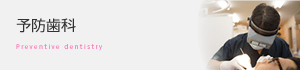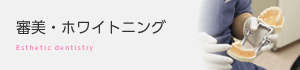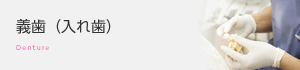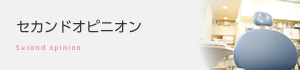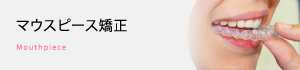10月, 2018年
野菜や果物で口臭は予防できる? [2018年10月15日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「野菜や果物で口臭予防することの問題」です。口臭はエチケットの問題でもありますから、多くの人が普段から気を遣っていると思います。 特に女性は食事の後、食べた食材に […]
噛み合わせを悪くさせてしまう可能性がある子供の癖って何ですか? [2018年10月01日]
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。 今回のテーマは「噛み合わせが悪くなる子供の癖」です。 ほとんどの子供は何らかの癖を持っており、親はそれを改善させるために頭を悩ませます。 さて、そんな子供の癖をなぜ改善させたい […]