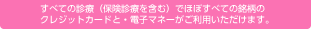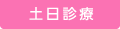BLOG
歯を磨いているのに口が臭くなってしまうのはなぜ?
2018年05月21日
歯を磨いているのに口が臭くなってしまうのはなぜ?
江東区門前仲町の歯医者さん、原澤歯科です。
今回のテーマは「歯磨きしたのに口臭がするケース」です。
自分の口臭が気になった時、誰もがするのは歯磨きでしょう。
確かに、食べカスや食材などが原因による口臭なら歯磨きで解消できますからね。
しかし歯磨きしても口臭がするとなれば、
それは食べカスや食材以外の原因で口臭が起こっていることになります。
そこで、ここでは歯磨きしても口臭がするケースをテーマにして、
その場合の口臭の原因や対処方法について説明していきます。
このようなケースは決して稀ではないため、ぜひこの機会に覚えておくと良いですよ。

虫歯が原因のケース
虫歯になるということは口の中が不衛生な状態ということですから、プラークや歯石による口臭が起こります。
また、虫歯が進行することで口臭が発生することもあります。
歯が溶けて起こる口臭
虫歯が進行すると歯に穴があきますが、正確には歯が溶かされているのです。
本来硬い歯が虫歯菌によって溶かされると、歯はやわらかくなって発酵してしまいます。
この発酵によって発生する発酵臭が口臭になるのです。
神経が腐って起こる口臭
虫歯が神経まで進行すると、やがて虫歯菌が神経を腐らせて口臭が起こります。
最も、虫歯が神経まで進行すれば口臭以前に酷い激痛を感じるため虫歯を自覚するでしょう。
このため、虫歯を放置することさえしなければこの類の口臭が起こるまでの事態にはなりません。
膿みが出て起こる口臭
歯の神経が死ぬと根管内に細菌が増殖し、歯の根の先には膿みの袋が発生します。
この膿みの袋は次第に大きくなり、やがて膿みが出てしまうことで口臭が起こります。
また、膿みの袋が大きくなると口臭以外にも周囲の骨を溶かす、蓄膿症になるなどの問題が起こります。
二次虫歯で起こる口臭
詰め物や被せ物で処置した歯に虫歯が再発することを二次虫歯と呼びます。
詰め物や被せ物は見た目こそ美しいですが、あくまでそれは人工物です。
その奥にある歯に虫歯が再発することで、プラークの発酵や血液などによる口臭が起こります。
<対処方法>
虫歯が原因で口臭が起こっている以上、虫歯を治療しなければ口臭は解消されません。
虫歯の場合は治療も大切ですがそれ以上に予防が大切です。
毎日の歯磨きだけでなく定期検診を受けるなどして予防効果を高めましょう。
また、二次虫歯については詰め物や被せ物をセラミックにすることで予防しやすくなります。
歯周病が原因のケース
歯磨きしても口臭が解消されない場合、原因として最も可能性が高いのは歯周病です。
また、歯周病による口臭は他の口臭に比べて臭いがキツイと言われています。
なぜ歯周病で口臭が起こるのか
歯周病になると口の中で細菌が繁殖するため、プラークや歯石による口臭が起こります。
ちなみに歯周ポケットの溝にもプラークや歯石が溜まるため、見えないところでも細菌が繁殖します。
さらに歯周病によって歯肉が炎症を起こすと、歯肉から膿みが出たり出血したりもします。
これらの膿みや出血によって出た血液もまた口臭の原因になるのです。
特に膿みが出たことで起こる口臭は臭いが酷く、周囲の人が不快に感じてしまうほどです。
歯周病は元々自覚症状が少ないため、ある意味口臭は歯周病であることを知らせるSOSのサインです。
<対処方法>
口臭の原因である歯周病を治療することで口臭は解消されますが、
歯周病の場合はそもそも自分が歯周病であることに気づきにくいのが問題です。
このため、定期検診を受けて定期的に口の中の健康状態を歯科医にチェックしてもらいましょう。
また、歯周病を予防するには歯磨きや定期検診だけでなく生活習慣を改善し、免疫力を高める必要があります。
胃の病気が原因のケース
「口臭=口の中の健康状態に原因がある」と考えがちですし、確かにその可能性は高いでしょう。
しかしそうではなく、胃の病気によって口臭が起こることもあります。
胃炎で起こる口臭
胃炎になって胃酸が出にくくなると、食べた物が未消化で胃の中に長く停滞した状態になります。
そうなると本来腸で行われるはずの発酵が胃の中で行われてしまい、
その時発生した発酵臭が肺に入り込んで呼吸時に口臭を引き起こしてしまいます。
胃がんで起こる口臭
胃がんになると、がんの壊死によって臭いのキツイ成分が発生します。
その成分はやがて血液の中に吸収され、血管を通って肺に入り込みます。
そうすると呼吸時に排出されますが、その成分の臭いがキツイことで口臭が起こってしまうのです。
十二指腸潰瘍で起こる口臭
口臭が起こるまでの流れは胃炎と全く同じです。
消化不良によって食べた物が消化されず、胃の中でそれが発酵してしまいます。
この発酵時に発酵臭が発生し、肺に入り込むことで呼吸時に口臭を引き起こしてしまいます。
逆流性食道炎で起こる口臭
逆流性食道炎とは胃液が食道に逆流する病気です。
嘔吐時の臭いから分かるとおり、胃液は酸っぱくツンとした臭いを放ちます。
その胃液が逆流することで口臭の原因になりますし、さらに胃の臭いも混ざるためキツイ口臭が起こります。
<対処方法>
胃の病気の多くは生活習慣やストレスが原因とされていますが、
詳しい予防方法や治療方法は専門の医科でないためハッキリとは言えません。
ちなみに、この場合のポイントは「いかにして口臭の原因が胃の病気にあると気づくか」にあるため、
口臭を自覚した時には口臭外来を受診し、確実な原因の特定をしましょう。
便秘が原因のケース
便秘になると排泄物が腸の中に溜まるため、腸内環境が悪化して大腸菌などの悪玉菌が増殖します。
その影響で腸内の排泄物が腐敗しますが、この時腐敗した排泄物から有害物質が発生します。
最も、本来ならこの有害物質は便と一緒に排泄されるので大きな問題はありません。
しかし便秘になると排泄が行われないため、有害物質は腸内に残って腸壁から吸収されてしまいます。
そして腸壁から吸収されることで血液中に溶け出し、血液中に溶け出すことで血管を通じて全身に回ります。
そして肺に回ってしまうことで呼吸時に口臭が起こり、この場合の口臭は便臭に近いものになります。
<対処方法>
便秘を解消する必要がありますが、そもそも便秘が起こるのは腸内環境が悪化しているからです。
このため食物繊維や乳酸菌を接触的に摂取し、腸内の善玉菌を増やすことを目指してください。
また、腸内環境を整えるためにはストレスの解消や適度な運動も大切です。
特に女性はダイエットなどで腸の動きを鈍くさせるため、男性に比べて便秘になりやすくなります。
唾液の分泌量の低下が原因のケース
唾液の分泌量の低下は虫歯や歯周病になるリスクを高めますが、口臭を引き起こす原因にもなります。
唾液の質自体は人それぞれ異なるものの、方法次第で分泌量を高めることは可能です。
なぜ唾液の分泌量が低下すると口臭が起こるのか
唾液には酸素が含まれているため、唾液の分泌量の低下は口の中が酸欠状態になることを意味します。
さて、口の中には様々な種類の細菌が存在していますが、
その中の1つに酸素を嫌う特徴を持った嫌気性菌と呼ばれる細菌があります。
酸素を嫌うということは酸欠状態を好むということですから、
唾液の分泌量が低下した口の中は嫌気性菌にとって最も好む環境になるのです。
そうなると嫌気性菌の働きが活発になります。
嫌気性菌の働きとはプラークを分解することで、働きが活発になることでより多くのプラークを分解します。
プラークは細菌の塊ですから、それが分解されることで嫌な臭いが発生します。
多くのプラークが分解されればそれだけ嫌な臭いも多く発生しますから、それが口臭となってしまうのです。
<対処方法>
唾液の分泌量を高めることで嫌気性菌の働きを抑制できます。
水分を摂取する、気分をリラックスさせて副交感神経を高める、ガムを噛む、鼻呼吸をする、
これらの方法で唾液の分泌量を高めて嫌気性菌の働きを抑えてください。
ただし「ガムを噛む」の場合は虫歯のリスクを考慮してシュガーレスタイプのものにしましょう。
まとめ

いかがでしたか?
最後に、歯磨きしたのに口臭が発生するケースについてまとめます。
1. 虫歯が原因のケース :プラークや歯石によるものだけでなく、以下のような原因もある
・歯が溶けて起こる口臭 :歯が溶かされることで発酵し、その時発生する発酵臭が口臭になる
・神経が腐って起こる口臭 :虫歯菌によって神経が腐ってしまうと口臭が起こる
・膿みが出て起こる口臭 :歯の根の先に発生した膿みの袋から膿みが出ることで口臭が起こる
・二次虫歯で起こる口臭 :二次虫歯になると、プラークの発酵や血液などによる口臭が起こる
2. 歯周病が原因のケース :口臭の原因として最も可能性が高く、歯周病による口臭はキツイ臭いがする
・なぜ歯周病で口臭が起こるのか :細菌の繁殖、プラークや歯石、歯肉から出た膿みなどが原因
3. 胃の病気が原因のケース :口臭は口の中に原因があるとは限らず、胃の病気が原因のケースもある
・胃炎を起こる口臭 :胃の中で食べ物が発酵し、その時発生した発酵臭が口臭を引き起こす
・胃がんで起こる口臭 :がんの壊死によって発生した成分が呼吸時に排出されて口臭になる
・十二指腸潰瘍で起こる口臭 :胃炎と同じで、食べ物の発酵によって発生した発酵臭が口臭になる
・逆流性食道炎で起こる口臭 :胃液の臭いと胃の臭いが混ざったキツイ口臭が起こる
4. 便秘が原因のケース :排泄物の腐敗によって発生した有害物質が口臭を引き起こす
5. 唾液の分泌量の低下が原因のケース :唾液の分泌量の低下は口臭の原因にもなる
・なぜ唾液の分泌量が低下すると口臭が起こるのか :嫌気性菌の働きが活発になるため
これらのことから、歯磨きしたのに口臭が発生するケースについて分かります。
口臭にはこのような原因が考えられるため、単に「口臭がする」だけで原因を特定するのは困難です。
正確にはどんな口臭がするのかである程度特定できますが、それでも断言するには根拠が不充分です。
中には深刻な病気が原因のケースもあるため、
口臭が気になった時には歯科医に相談、もしくは口臭の専門外来を受診すべきでしょう。